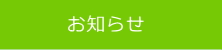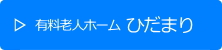トップ表示記事の記事
設立法人 公益社団法人石川勤労者医療協会
理事長 島 隆雄
所長 加藤 真一
診療科目 内科・リウマチ膠原病科
基本診療料の届出
機能強化加算 令和 4年 4月届出
医療DX推進体制整備加算 令和 6年 7月届出
時間外対応加算1 平成24年 5月届出
特掲診療料の届出
外来・在宅ベースアップ評価料 令和 6年 6月届出
ニコチン依存症管理料 平成29年 5月届出
在宅療養支援診療所 令和 4年10月届出
在宅時医学総合管理料 平成19年 2月届出
在宅がん医療総合診療料 平成19年 2月届出
CT撮影及びMRI撮影 平成27年 9月届出
■機能強化加算
当院では「かかりつけ医」として必要に応じ以下の対応を行っています。
・受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要な薬の管理を行います。
・必要に応じ専門の医師・医療機関をご紹介します。
・健康診断の結果に関する相談など、健康管理に関する相談に応じます。
・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
・夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。
■医療DX推進体制整備加算
・当院では、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を行います。
・マイナ保険証を促進する等、医療DXに係る取り組みを進めます。
■明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
■一般名処方加算
当院では後発医薬品の使用推進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
令和6年10月1日より、患者様が一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)への変更を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、ご負担いただくことがございます。
保険外負担に関する事項
文書料等の保険外負担につきまして、実費のご負担をお願いしています。
詳細は「自費料金表」をご覧ください。
当院は2023年10月よりインボイス発行事業者となっております。
適格請求書発行登録番号はT9220005000023です。
上記の番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでも確認できます。
自治体検診について
(すこやか検診 白山市特定健診・長寿健診 いきいき健診)
当院では、金沢市・白山市・野々市市が実施する自治体検診(特定健診・がん検診など)が受けられます。対象となる方には自治体より「受診券」が配布されておりますので、受診の際に保険証とともにご持参ください。
年齢によって受けることのできる健診内容が変ったりします。詳しくは、自治体より配布されているご案内をご覧いただくか、上荒屋クリニック受付までお尋ねください。ご予約もお取りできますので、お気軽にお問い合わせください。
金沢市 すこやか検診 5月~10月
白山市 特定健診・長寿健診 6月~10月
野々市市 いきいき健診 6月~9月
上荒屋クリニック
リウマチ診療分野における関節エコーの重要性はますます高まって来ています。
関節リウマチにおいては、リアルタイムの滑膜炎の病勢をみることに特に有用で、予後予測にも有用と考えられています。最近では他のリウマチ性疾患の評価にも使われてきています。また、侵襲性がなく、検査費用も安いというメリットがあります。
2014年度の当院の取り組み
6月に、パリにて関節エコーのIntermediate courseを受講しました。
これは、EULAR(欧州リウマチ学会)に先駆けて3泊4日で行われた研修会で、合宿のような形で関節エコーに集中して勉強するものです。講師にはこの分野でトップの方たちが勢ぞろいしていました。
一緒に回ったグループの他の4人の先生は、国籍がスペイン、ベルギー、オランダ、サウジアラビアで、内3名は女医の方々で、バラエティに富み、それぞれの国の医療事情なども興味深く聞けました。
9月に、当院の2人の技師が、東京で開催された Academy of Imaging のワークショップに1泊2日にて参加しました。関節エコーの指導を行うのは日本を代表する方々で、大変勉強になり、刺激となったようでした。

御報告が遅れましたが、昨年11月下旬にボストンで開催された米国リウマチ学会に参加して来ました。関節リウマチ(RA)の分野でも興味深い発表は多かったのですが、全体として、病態の解明や新薬の創薬という点では、乾癬性関節炎に関する発表がより盛り上がっているようでした。2013年のウステキヌマブ(抗IL12/23製剤)、2014年のアプレミラスト(PDE4阻害剤)、さらに今後認可される見通しのセクキヌマブ(抗IL-17A抗体)、イクセキツマブ(抗IL-17A抗体)、ブロダルマブ(抗IL-17受容体抗体)などの薬剤に関する報告が、シンポジウムを含め多く、RAに対する生物学的製剤が次々と市場に出た時の熱気に似ているかもしれません。日本では欧米に比べると罹患率は低く、リウマチ医の注目度はやや低いかもしれませんが、重症例では深刻な病気であり、皮膚科医とリウマチ科医の密接な連携も今後の課題かと思われます。 詳細はこちら
2014年12月7日に石川県地場産業振興センターにてリウマチ医療療養懇談会を開催させていただきました。
今年は開催時期が遅く、当日、風雪にて天候が非常に悪かったこともあり、御参加いただけたのは例年の半数程度でした。
2014年度のリウマチ医療におけるトピックスを、特に直前の11月に行われた米国リウマチ学会(ACR)の報告などを中心に、基礎から臨床までお話しさせていただきました。今回、米国リウマチ学会にて新しいRA治療指針の草稿版が発表されたこともあり、それを2013年に発表されたヨーロッパリウマチ学会(EULAR)の治療指針、今年発表された日本リウマチ学会(JCR)の診療ガイドラインとの比較検討も行ってみました。
足元の悪い中、御参加いただけた皆様に深謝致します。